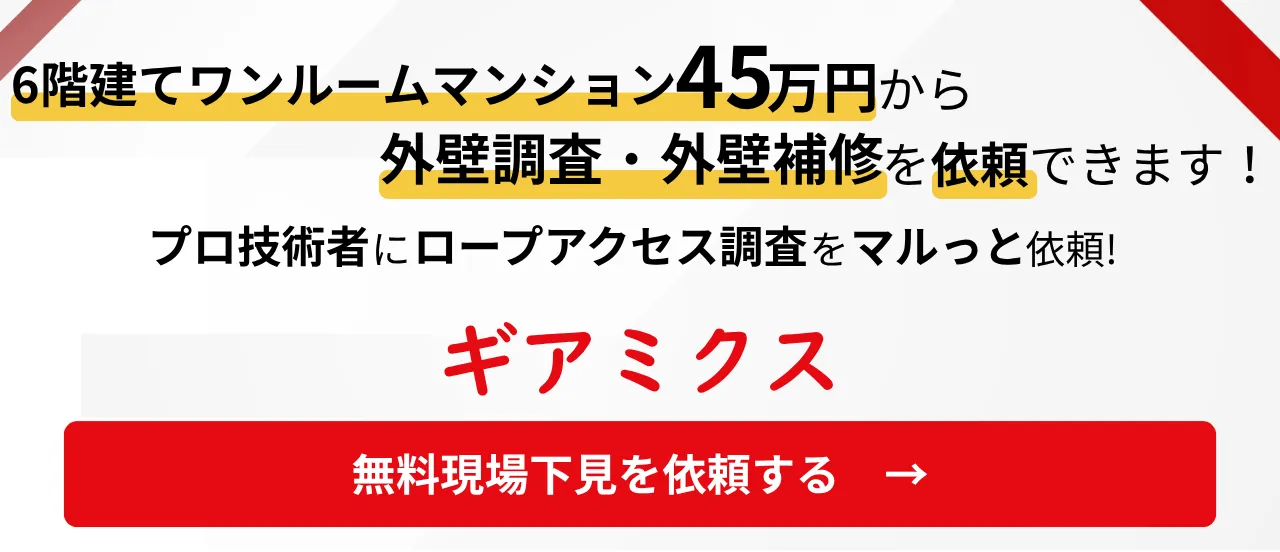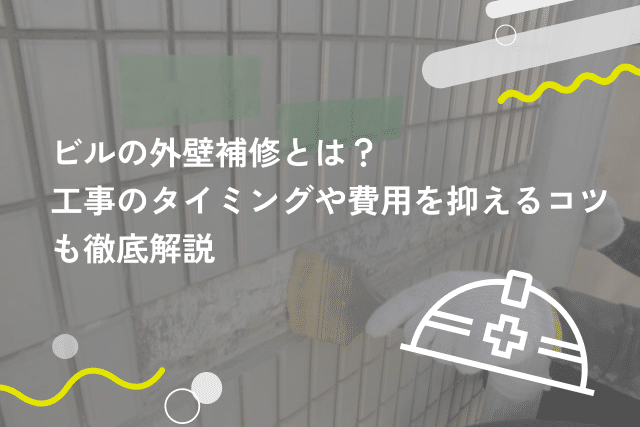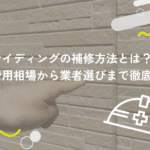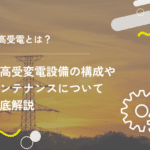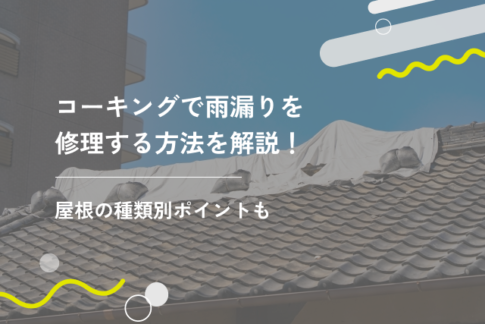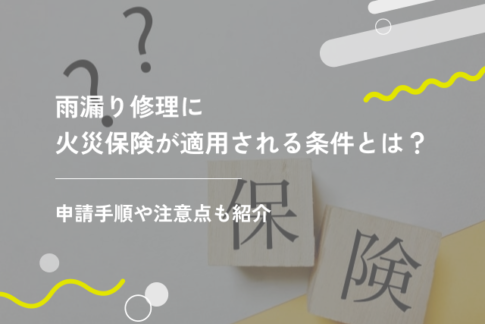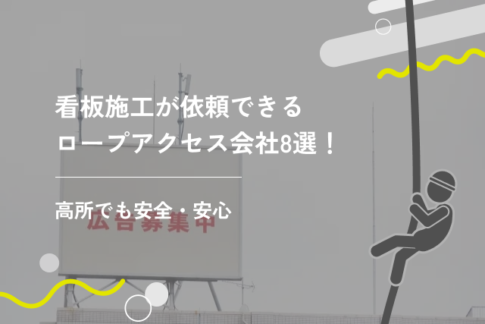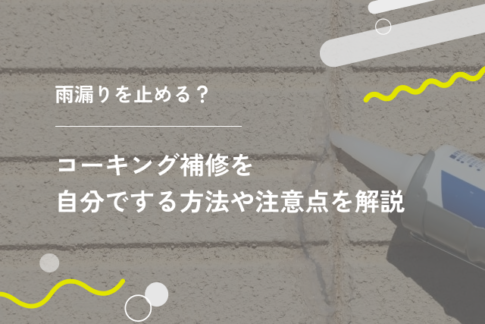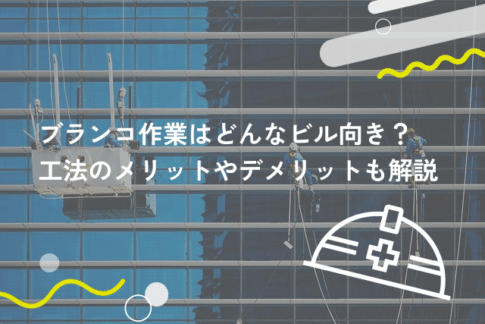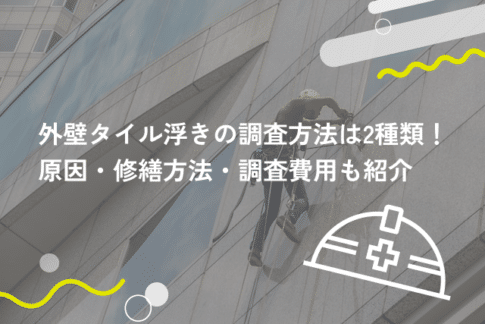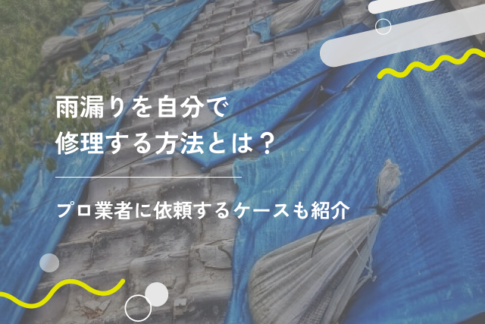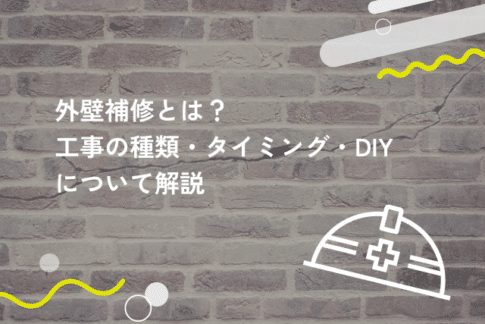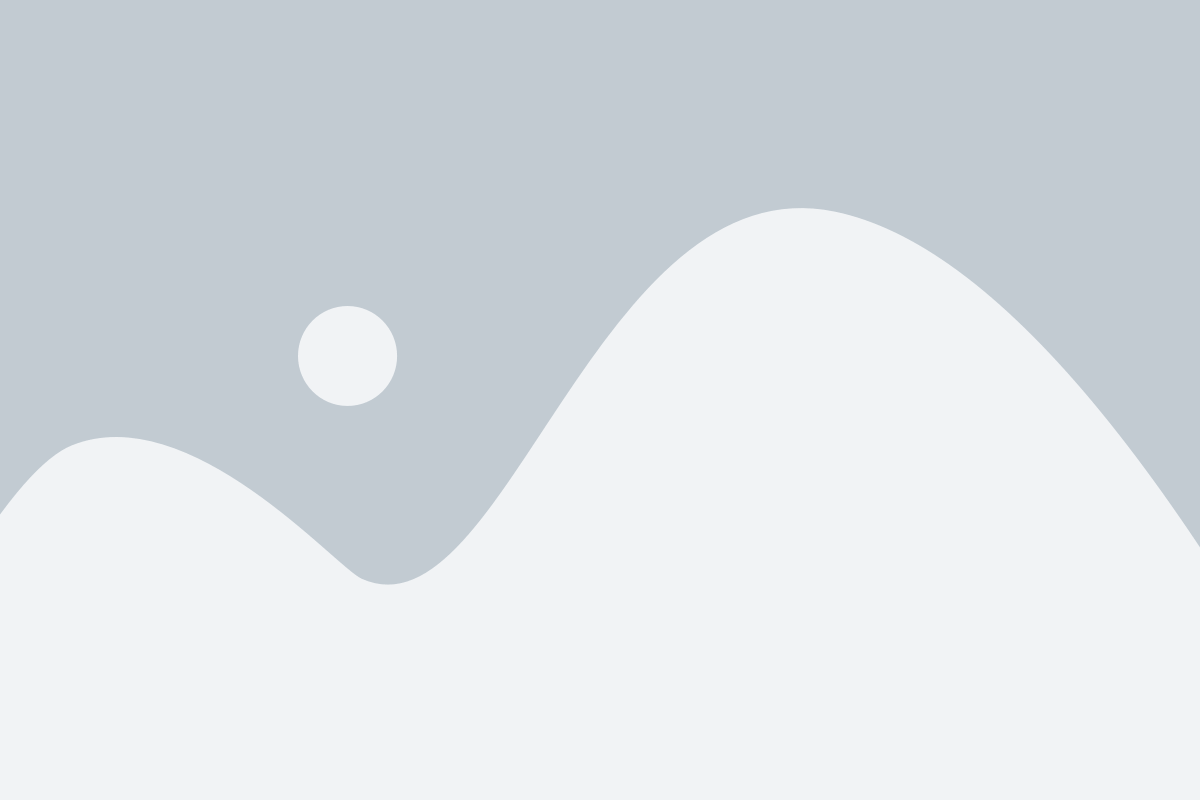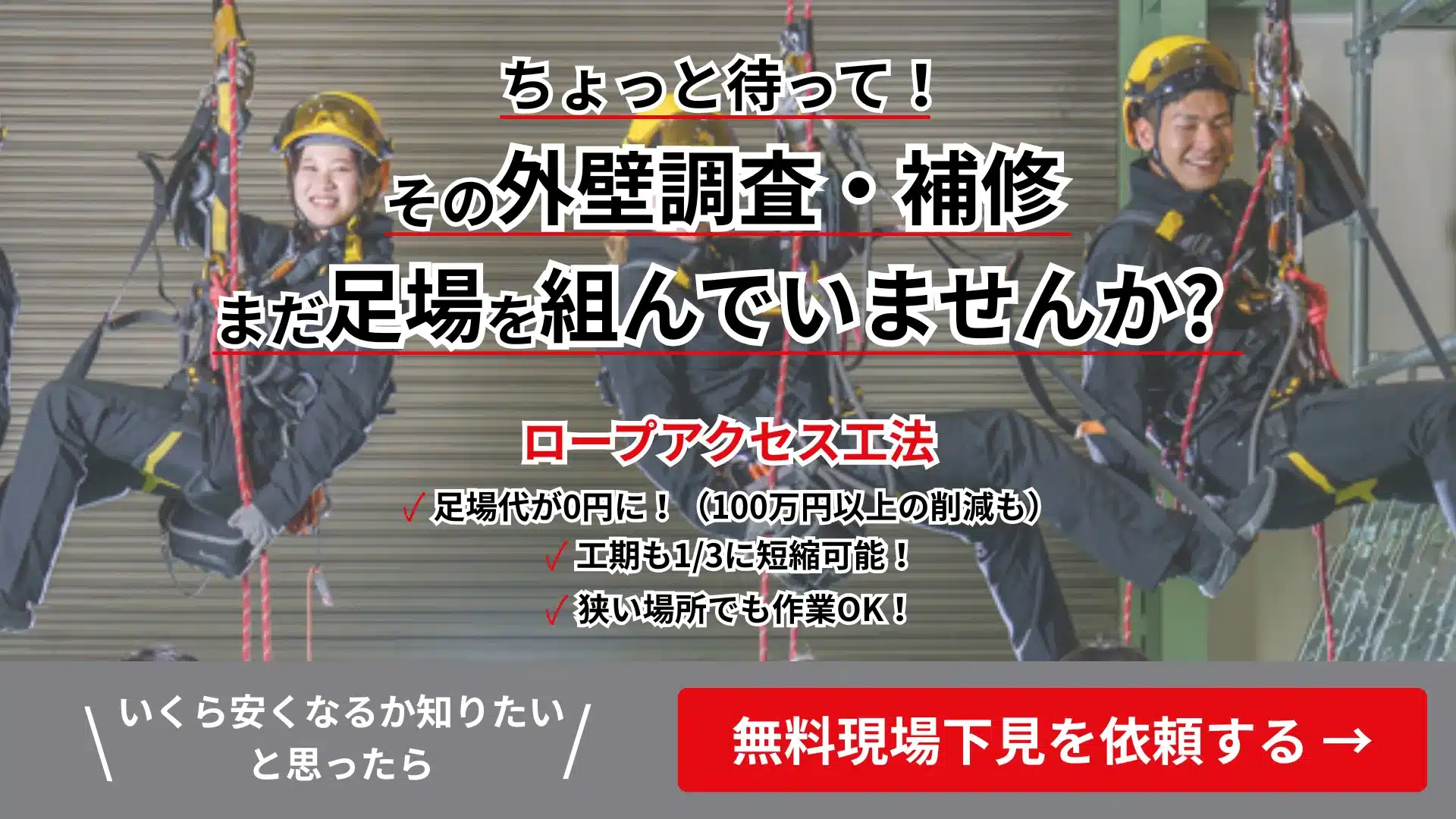ビルメンテナンスは、様々な建物の維持・管理に欠かせない存在です。
しかし、ビルメンテナンスはどのようにして行われるのでしょうか。
本記事では、ビルメンテナンスの基礎知識を解説します。
ビルメンテナンス業者選びのポイントや必要な資格も、あわせてご覧ください。
また、今すぐ外壁調査・外壁補修を依頼したい方は「ギアミクス」がおすすめです。
- 250件以上の施工実績
- 足場不要のロープアクセス工法で大幅コストダウン
- 最短1日で調査完了
- 調査から補修までワンストップ対応
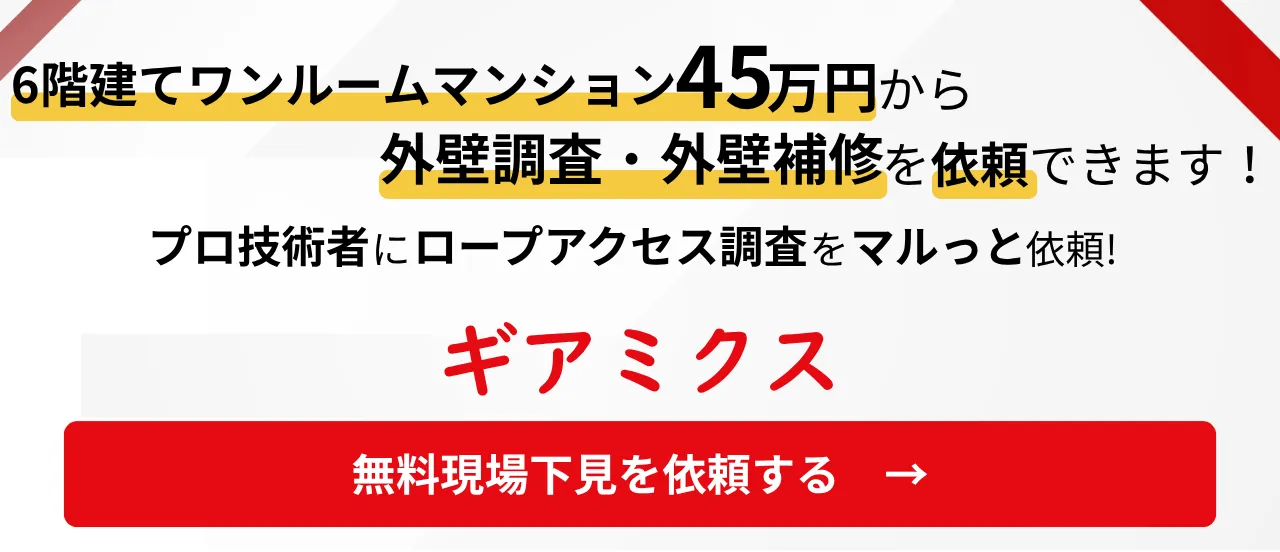
目次
ビルメンテナンスが請け負う6つの主幹業務とは?

ビルメンテナンス業者が、請け負う業務はおもに下記の6つです。
- ビルの外観・内観をメンテナンス「清掃管理業務」
- ビル内の衛生環境をメンテナンス「衛生管理業務」
- ビルの機器メンテナンス「設備管理業務」
- ビルの劣化・消耗をメンテナンス「建物・設備保全業務」
- ビルと人の安全を守る「警備・防災業務」
それでは、さっそくそれぞれを解説しますので、見てみましょう。
業務1.ビルの外観・内観をメンテナンス「清掃管理業務」
清掃管理は、床面だけでなく、部屋全体がバランスのとれた美観を維持するための作業です。
壁面・扉・オフィスの備品など、立体的な視点で業務を遂行し、各部屋の美しさを維持します。
清掃管理の専門家としては、ビルクリーニング技能士や建築物清掃管理表化資格者(ビルクリーニング品質インスペクター)が知られています。
床材・壁材には、金属材や石材など多様な素材が使用されており、素材に合ったメンテナンスの知識が必要です。
近年では、汚れてから清掃する「事後清掃」から、汚れを持ち込ませない「予防清掃」へと切り替わりました。
予防清掃は、病院や介護施設などのように、汚れ・ウイルスを持ち込んではならない建物にも有効です。
清掃管理は、美しい見た目だけでなく、より安心して過ごせる空間作りが可能です。
ビル内の衛生環境をメンテナンス「衛生管理業務」
衛生管理は、建築物衛生法に基づいて行われる、ビル内の衛生的な環境維持のための作業です。
衛生管理業務の業務は、下記のように多岐に渡ります。
- 空気環境管理業務:建築物環境衛生管理基準(厚生労働省)に基づいて建物内の空気を清潔に保つ業務。浮遊粉塵の量・一酸化炭素濃度・二酸化炭素濃度・温度など、基準を満たせるよう、定期的な測定と調整を実施する。
- 給水・排水管理業務:貯水槽清掃や定期的な水質検査のほか、排水槽・排水管・浄化槽などの掃除や設備の保守管理を実施する。
- 廃棄物処理業務:商業施設の廃棄物は自治体の処理施設に持ち込む、または専門業者に収集・処理を委託しなければならないため、業務を代行する。
- ネズミ・害虫防除業務:ネズミ・ハエ・ゴキブリ・ダニ・ノミなどの侵入防止や駆除を実施。建築基準法で定められた特定建築物の場合は、6カ月ごとに生体調査を実施し、ネズミや害虫の発生場所・生息場所・侵入経路を調べ、必要に応じて駆除する。
ビル内の衛生状態は、利用者のストレスを減少できるほか、アレルギーや病原菌への対策という観点からも重要です。
ビルの機器メンテナンス「設備管理業務」
設備管理は、ビル内設備機器の運転・監視・点検・整備・保全に加え、記録の保存・分析が業務です。
現代の建物には、エレベーター・エスカレーター・エアコン・照明など、様々な設備機器が備わっています。
設備機器は中央監視盤で監視され、コンピュータによって自動的にコントロールされています。
そのため設備管理には、地球温暖化対策や各コンピューター・システムについての知識が必要です。
そういった背景をもとに、平成8年には「ビル設備管理技能士(1・2級)」が、平成28年には環境省から「エコチューニング技術者(1・2級)」の制度が開始。
設備管理の業務は、使いやすく、環境に優しい建物に貢献する業務です。
ビルの劣化・消耗をメンテナンス「建物・設備保全業務」
建物・設備保全の業務は、下記設備の維持・管理を行います。
- 受変電設備
- 発電機械
- ボイラー設備
- 冷凍機設備
- 建物の空気環境
- 飲料水貯水槽
定期点検や建物利用者からの声をデータ化・蓄積し、建物および機器の経年劣化・消耗に応じた対応が行われます。
受変電設備のように法定点検が必要となるケースもあり、建物・設備管理はビルメンテナンスの中でも欠かせない存在です。
建物の受変電設備に関しては「10分でわかる受電設備!基礎知識から法定点検までを徹底解説」をご覧ください。
ビルと人の安全を守る「警備・防災業務」
警備防災は、災害や犯罪から利用者を守るための業務です。
当記事をご覧になっている方の中にも、ビルに常駐する警備員を見た経験があるのではないでしょうか。
ビルに常駐する警備員は、一定の教育を受け、日常的に防犯・防災業務に従事しています。
さらに近年では、監視カメラをはじめとした、防犯・防災設備のシステム化が進んでいます。
そのため、ビルに常駐する警備員だけでなく、防災センターの役割が重大化。
より専門性の高い知識が必要とされ、警備業法で定められた基準を順守可能な、認定業者のみが対応可能です。
落壁事故を予防する「外壁調査」
ビルは建築基準法で、定期的な外壁調査が義務化されています。
外壁調査の種類は、おもに以下の4種類。
- 目視調査:外壁を目視で確認してヒビや割れがないかを確認する。
- 打診調査:専用工具を用いて外壁を叩き、音の違いから問題の有無を調査する。
- 赤外線調査:外壁を赤外線カメラで撮影し、温度の違いから外壁の剥がれや浮きの有無を調査する。
- ドローン調査:ドローンに赤外線カメラを搭載し、外壁を撮影する調査。
建築基準法で定められた特定建築物は1~3年ごと、それ以外のビルは10年に1度の全面打診等調査が義務化されています。
打診調査が前面に出ている理由は、外壁調査の種類の中でも信ぴょう性が高いとされているため。
打診調査は、足場を要するためコストが膨れがちなのが課題ですが、近年では足場が不要なロープアクセス工法が注目されています。
ロープアクセス工法については「ロープアクセス工法とは?基礎・メリット・デメリットを解説」をご覧ください。
ビルメンテナンスを導入する5つのメリット

ビルメンテナンスを行うメリットは、おもに以下の5つです。
- 消防法対策にビルメンテナンス有効
- ビルメンテナンスで建築基準法の対策が可能
- 定期的なビルメンテナンスでビル管法対策が可能
- ビルメンテナンスで電気事業法対策が可能
- 建物の寿命がビルメンテナンスで伸びる
それぞれのメリットについて、より詳しく見てみましょう。
ビルメンテナンスで消防法の対策が可能
建物には「防火対象物定期点検報告」と「消防用設備点検報告」が、消防法で義務付けられています。
いずれも特定建築物が対象で、火災・防災を目的としており、点検を行わない場合はペナルティが課せられるケースも。
最大のペナルティを課せられた場合、30万円以下の罰金または拘留されます。
上記のようなリスクを回避するためにも、それぞれの設備点検・報告は必須です。
ビルメンテナンスで建築基準法の対策が可能
ビルメンテナンスは、建築法第12条の定期報告に対応可能です。
建築基準法第12条では、建築物・建築設備・防火設備・昇降機の定期検査・報告が求められます。
この法律は、建物の安全確保により、利用者の命や健康を守るのが目的。
一定以上の面積がある特定建築物に該当する場合、上記の法律に関わります。
建物が該当するかどうか不安な場合は、メンテナンス業者に問い合わせてみると安心でしょう。
ビルメンテナンスでビル管法対策が可能
ビル管法では、建物が衛生的な環境を維持できているかについて、点検と報告が求められます。
詳しくは、厚生労働省「建築物環境衛生管理基準について」に掲載されている通りです。
建築基準法第12条と同様に、特定建築物が該当します。
衛生環境が守られない場合、利用者のイメージダウンにつながるほか、保健所からの指導を受ける可能性があるため注意しましょう。
ビルメンテナンスで電気事業法対策が可能
建物の電気設備には、定期点検が必要です。
月次点検を要する設備と、年次点検を要する設備に分けられ、建物の所有者・管理者には電気主任技術者の専任も求められます。
設備の点検方法として知られる、模擬負荷試験と実負荷試験については「実負荷試験と模擬負荷試験の違いとは?非常用発電機の点検周期も解説」に詳しく掲載しています。
対象となるのは特定建築物ですが、点検・報告を怠った場合は罰則もあるため、定期的に行うようにしましょう。
建物の寿命がビルメンテナンスで伸びる
建物の躯体を長期間にわたって維持するには、外部からのダメージ軽減が有効です。
外部からのダメージを軽減するには、外壁がしっかりと役割を果たしていることが大切なため、外壁調査や外壁のメンテナンスによって保たなければなりません。
ビルの内部環境は、利用者に対する印象を決める大事な要素です。
そのため、衛生管理や建物設備・保全などによって、清潔さと快適さを維持するのが有効です。
上記のように、外部と内部の両面から定期的にメンテナンスを実施すると、建物の長寿化に期待できます。
また、今すぐ外壁調査・外壁補修を依頼したい方は「ギアミクス」がおすすめです。- 250件以上の施工実績
- 足場不要のロープアクセス工法で大幅コストダウン
- 最短1日で調査完了
- 調査から補修までワンストップ対応
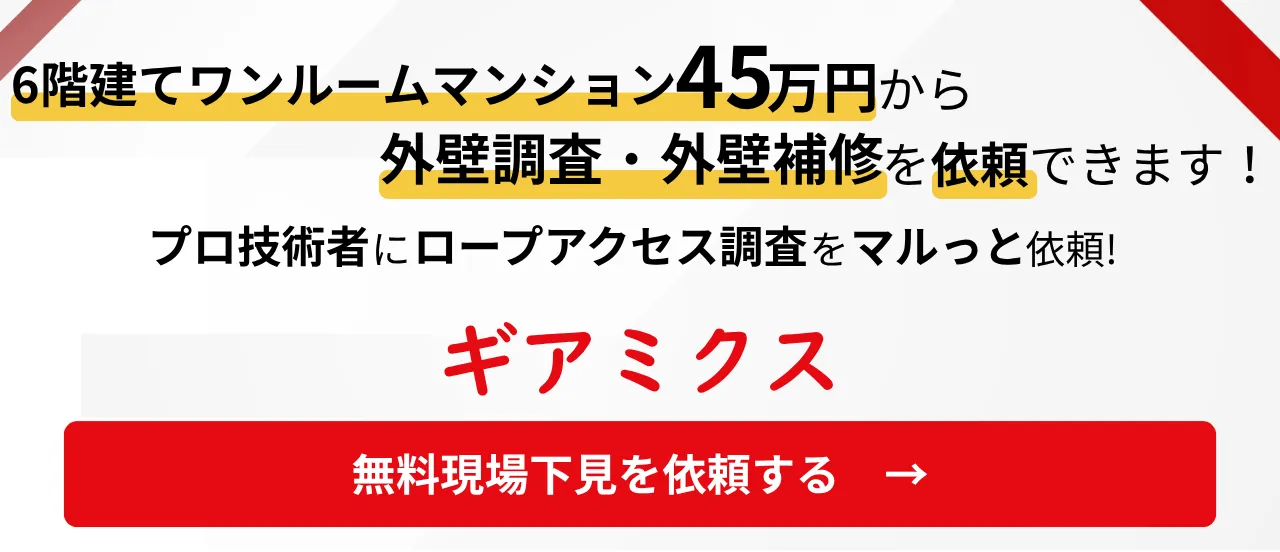
義務化された点検と頻度の一覧

建築基準法や建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)では、さまざまな点検を義務付けています。
点検の実施頻度は以下の通りです。
- 特定建物定期検査:1~3年に1回
- 建築設備定期検査:1年に1回
- 消防設備点検:1年に2回
- 室内空気環境測定:2カ月に1回
ビルメンテナンスで求められる資格とは?
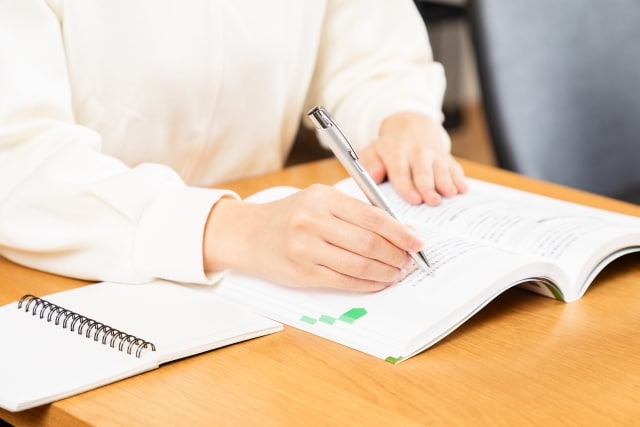
ビルメンテナンスでは、業務に応じて資格が必要になる場合もあります。
本章では、ビルメンテナンスに必要な資格を解説します。
第二種電気工事士
第二種電気工事士の概要は以下の通りです。
- 600V以下の低圧電気設備の工事に必要な国家資格
- 屋内配線工事・照明器具設置・コンセントやスイッチ取付・エアコン設置などがおもな業務
第二種電気工事士は「ビルメン4点セット」としても知られており、電気設備の保守点検に必要な資格です。
第三種電気主任技術者
第三種電気主任技術者の概要は以下の通りです。
- 電圧が50,000Vボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)の工事・維持・運用の保安を監督する国家資格
- 電気設備の定期点検・異常時対応・維持・運用・安全管理などが業務
第三種電気主任技術者は、ビルや工場などで使われる電気設備の保守管理に必要です。
第三種冷凍機械責任者
第三種冷凍機械責任者の概要は以下の通りです。
- 1日の冷凍能力が100t未満の製造施設で使う冷凍設備の保安業務に従事できる国家資格
- 冷凍設備の保守点検・無資格者の監督・点検結果の確認と保管・修理工事の調整と立ち合いなどが業務
第三種冷凍機械責任者は、ビルメンテナンス業界で「ビルメン4点セット」のうちのひとつとしても知られるメジャーな資格です。
危険物取扱者乙種4類
危険物取扱者乙種4類の概要は以下の通りです。
- ガソリン・灯油などの石油類の取り扱いに必要な国家資格
- ビル内にあるボイラーの燃料となる重油の管理がおもな業務
危険物取扱者乙種4類は「ビルメン4点セット」のひとつで、比較的取得が容易な資格として知られています。
二級ボイラー技師
二級ボイラー技師の概要は以下の通りです。
- 伝熱面積が25㎡未満のボイラーを取り扱える国家資格
- 給湯・冷暖房などの設備に必要なボイラーの運転・監視・保守管理などが業務
二級ボイラー技師は「ビルメン4点セット」のひとつで、筆記試験の合格と講習の受講で獲得できます。
消防設備士(乙4・乙6)
まずは消防設備士乙4種の概要です。
- ビルに設置されているし自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備などの点検・整備ができる国家資格
- 自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備などのセンサーや火災警報器の動作確認・配線やケーブルの異常確認などが業務
続いて、消防設備士乙6種です。
- 消火器の点検・整備ができる国家資格
- 消火器の定期点検がおもな業務
消防設備士は、ビルを火災から守るための業務に必要な資格です。
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
建築物環境衛生管理技術者(通称:ビル管理士)の概要は以下の通りです。
- 建築物の環境衛生を維持管理できる国家資格
- 空気環境・給排水・清掃・害虫駆除・廃棄物処理・水質検査などが業務
- 特定建築物では資格保持者を選任して監督させなければならない
建築物環境衛生管理技術者は、ビルを快適に利用するために欠かせない存在です。
管理業務主任者
管理業務主任者の概要は以下の通りです。
- マンション管理会社が管理組合に業務委託する際に不可欠な国家資格
- マンションの管理委託契約についての重要事項説明・管理業務の報告などが業務
管理業務主任者は、マンション管理のプロフェッショナルとして、マンション管理を適正化するのも役割です。
マンション管理士
マンション管理士の概要は以下の通りです。
- マンションの維持管理に関するコンサルティングができる国家資格
- 管理組合の管理者や区分所有者の相談に応じた助言・指導・援助などが業務
マンション管理者は、大規模修繕計画の計画立案や住民間のトラブルへの対応など、幅広く対応します。
マンションの補修の詳細は「マンション外壁の種類を解説!選び方や補修・塗装の必要性・作業内容」をご覧ください。
ビルクリーニング技能士(1級・2級・3級)
ビルクリーニング技能士の概要は以下の通りです。
- 数字が若いほど高度な知識とスキルが求められ、1級は現場責任者として働ける国家資格
- 2級・3級は清掃業務、1級は清掃業務従事者の監督がおもな業務
ビルクリーニング技能士の1級は7年以上、2級は2年以上の実務経験が必要です。
ビルクリーニング技能士1級は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で事業登録に必要な人的要件として定められています。
ビル設備管理技能士(1級・2級)
ビル設備管理技能士の概要は以下の通りです。
- ビルの電気・空調・給排水設備などの運転監視・点検・メンテナンスができる国家資格
- 1級と2級の違いは専門性の高さで携わる業務に大きな差はない
ビル設備管理技能士は、2級で2年以上、1級は7年以上の実務経験が受験に必要です。
資格保持者がいるビルメンテナンス業者は、知識・スキルの両方が充足していると判断できます。
ビルメンテナンス業者選びの3つのポイントとは?

ビルメンテナンス業者選びは、慎重に行うべきです。
なぜなら、ビルメンテナンスの価格・品質などによって、建物の状態が大きく変わってしまうため。
ビルメンテナンス業者選びの、3つのポイントを解説します。
ビルメンテナンス業者選びのポイント
ポイント1.適正価格のビルメンテナンス業者を見極める
ビルメンテナンス業者は、コストだけでなく「なぜそれだけのコストが必要か」までをチェックしましょう。
ビルメンテナンス業者にとって、原価の大半は人件費です。
そのため、価格には大きな違いがあるケースは、ほとんどありません。
中には圧倒的な低価格を実現している業者もいますが、作業時間が少なく、十分なサービスを受けられない可能性があるため注意が必要です。
さらに「自社雇用のスタッフで対応しているかどうか」についても確認しておきましょう。
メンテナンス業務を外注している場合、委託費用が価格に上乗せされてしまいます。
ビルメンテナンス業者選びは、適正価格かつ適正なサービスが提供されるかが大きなポイントです。
ポイント2.ビルメンテナンスのサービス品質を確認
近年では、ビルメンテナンス業務がコンピュータによって自動制御されるケースが増えました。
それにともない、必要な教育体制にも変化が訪れています。
以前は「経験豊富=優良業者」という選び方でよかったかもしれません。
現代の建物においては、どのような教育体制で、どのような対応が可能なのかを確認が必要です。
たとえば外壁調査。
建物間の距離が近ければ、足場を設置できず、経験豊富なスタッフがいても対応は困難でしょう。
一方で、足場の設置不要で対応できるロープアクセス工法であれば、低コストで十分なサービス提供が可能です。
ビルメンテナンス業者のサービス内容は、建物に合っているのか、十分な品質なのかを確認すべきです。
ポイント3.ビルメンテナンスに適した有資格者がいるか
有資格者の有無は、最もわかりやすい判断材料の1つでしょう。
電気主任技術者・ボイラー技士などの資格取得には、一定以上の知識が必須。
つまり、有資格者がいるということは、専門機関が認めたスタッフが在籍する何よりの証ということ。
有資格者がいるメリットは、それだけではありません。
有資格者は、自身が持つ専門知識を周囲のスタッフに指導でき、より多くの有資格者を生み出す可能性があります。
教育体制は業者の考え方によるところが大きいですが、有資格者から、直接指導を受けられるのであれば安心です。
ビルメンテナンス業者をお探しの方へ

今回は、下記3つのポイントをお伝えしました。
- ビルメンテナンスは5つの業務に分けられる
- ビルメンテナンス業者は、価格・サービス品質・有資格者の有無を確認すべき
- ビルメンテナンスで、点検・報告義務を果たせる
株式会社ギアミクスは、外壁調査・衛生管理・電気設備管理などに対応しております。
ビルメンテナンスでお悩みの際は、ぜひお気軽にお問合せください。
また、今すぐ外壁調査・外壁補修を依頼したい方は「ギアミクス」がおすすめです。
- 250件以上の施工実績
- 足場不要のロープアクセス工法で大幅コストダウン
- 最短1日で調査完了
- 調査から補修までワンストップ対応